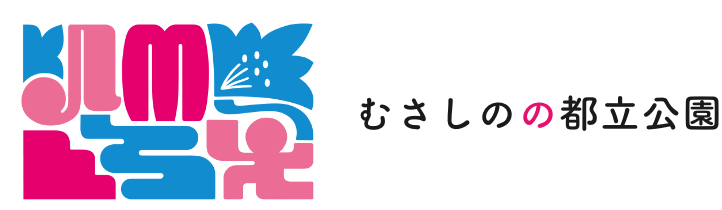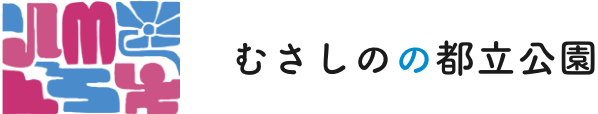VOLUNTEER
ボランティア情報
- むさしのの都立公園TOP
- ボランティア情報
公園づくり、地域づくりに参加しよう!

むさしのの都立公園 ボランティア募集!
むさしのの都立公園では、花壇づくりや自然保全、イベント運営など、様々なボランティア活動が行われています。公園ではどんな活動ができるの?
むさしのの都立公園では、花壇づくりや自然保全、
イベント運営など、様々なボランティア活動が行われています。

- 花壇づくり

- 自然保全

- イベント協力

- 学校・団体

- 企業(CSR)
気軽に参加できる、ボランティア体験型のイベントも開催しています。
気軽に参加してみたい!体験してみたい!という方は、
「イベント情報」をご確認いただくか、各公園までお問合せください。
活動団体のご紹介
各公園では、様々な団体が活動しています。皆さんも一緒に活動しませんか。 活動している場所(公園)や内容をご確認いただき、ご興味ある活動団体の連絡先へお問合せください!
01
野川公園
02
浅間山公園
03
浅間山公園
04
浅間山公園
05
六仙公園
学校、団体、企業(CSR)によるボランティア活動
学校・団体・企業等のボランティア活動受付中!
むさしのの都立公園グループでは、学校、団体、企業(CSR)による活動を受付けています。 これまで、外来種の引き抜き、清掃活動、イベントへの協力など公園づくりや地域づくりに関わる様々な活動が行われてきました。 活動を希望される方は、下記までお問合せください。
ボランティア活動に関するご相談は、下記より、お気軽にお問い合わせください。